筋トレ中に「バキッ」と首が鳴った、腹筋をしたら首がズキっと痛んだ…。そんな経験をきっかけに、トレーニングの継続を迷っていませんか?
実はこうした首の痛み、多くの場合「フォームの乱れ」や「ストレートネック」が関係しています。首の違和感を軽く見ていると、頭痛や腕のしびれに発展するケースも少なくありません。しかし、原因を正しく理解し、適切なケアを行えば、再発を防ぎながら安全に筋トレを続けることができます。
この記事では、筋トレで首が痛くなる原因やストレートネックとの関係性、冷やすべきか温めるべきかの応急処置法、痛みが出た時のトレーニング再開の目安、そして医療機関を受診すべき症状の見極め方まで、トレーニングと身体の両立を目指すあなたのために徹底解説します。
筋トレ中に首が痛くなる原因とは?
筋トレ中に首が痛む主な原因は、大きくフォームの問題と過度な負荷に分けられます。
まずフォームが崩れていると、本来鍛えたい筋肉以外に余計な負荷がかかり、首周りの筋肉(僧帽筋や首の深部筋など)を必要以上に緊張させてしまいます。
その結果、「首が張って痛い」「首筋を違えたような痛み」が生じることがあります次に、重量設定が自分の筋力に見合っていない場合も注意が必要です。
無理な重量を扱うと体が反射的に首や肩に力を入れて踏ん張ろうとするため、首の関節や筋に過剰なストレスがかかり痛みにつながります。
どのような種目が首を痛めやすいのでしょう?
ベンチプレスやショルダープレスでの首への負荷
ベンチプレスやショルダープレスなど、上半身を鍛える高重量の種目では、フォームの乱れから首に負荷が集中しやすくなります。
本来ベンチプレスでは胸や腕の筋肉を使いますが、肩甲骨の寄せが甘かったり頭の位置が不安定だったりすると、バーを押し上げる際に首を反らせて力んでしまうことがあります。
その結果、首周辺の筋肉に過剰な緊張が生じ、筋肉痛や筋を違えたような痛みにつながります。
また、ショルダープレス(肩の種目)でも、肩関節の可動域が狭かったり重量が重すぎたりすると、バーベルやダンベルを押し上げる際に首をすくめるクセが出てしまいがちです。
この「肩をすくめる動作」は僧帽筋など首肩の筋肉を強く緊張させ、首の後ろに痛みを引き起こす原因になります。
対処法:フォームの見直し – 首の痛みを防ぐには、正しいフォームの習得が第一です。
ベンチプレスでは肩甲骨をしっかり寄せて胸を張り、頭はベンチにつけたままにしましょう。リフト中に頭で押し付けて踏ん張る癖がある人は要注意です。ショルダープレスでは、重りを挙上する際に首がすくまない程度の重量から始め、肩甲骨を下げた安定した姿勢で動作することを心がけます。
また、動作中に痛みや違和感を覚えたら無理をせず中断する勇気も大切です。異常な痛みを感じたまま続けても良い結果は生まれず、かえって大きなケガにつながる恐れがあります。
腹筋運動で首が痛くなる理由
クランチやシットアップなどの腹筋種目で「首が痛い…」と感じる人も少なくありません。
これは主にフォームと筋力不足が原因です。腹筋が十分に使えていないと、上体を起こす際に首や肩の力で無理に引き上げようとしてしまい、首の前側の筋肉を過剰に使ってしまいます。
その結果、筋トレ中にも関わらず首が疲れて痛くなるという本末転倒な状況に陥ります。また、手を頭の後ろに組んで勢いよく上体を起こす癖がある場合、手で頭を引っ張って首を痛めることもあります。
対処法:サポートアイテムの活用– 腹筋運動で首を痛めやすい人は、フォーム矯正とともにサポートアイテムを活用しましょう。
折りたたんだタオルや専用のクッションを首の下に当てるだけでも、首への負担軽減に効果的です。また、動作中は顎を引きすぎず軽く天井を見るように意識し、腹筋の力で上体を起こすことに集中してください。首に手応えを感じたら回数を無理に増やさず、一度休んでフォームを確認することも大切です。
ストレートネックと筋トレの関係性は?
長時間のデスクワークやスマートフォンの使用習慣によって生じる「ストレートネック」は、近年若い世代にも急増しています。
ストレートネックとは、本来ゆるやかなカーブを描いている頸椎(首の骨)が真っ直ぐな状態になってしまったもので、その原因として代表的なのがスマホを見る際のうつむき姿勢です。
このような状態では首や肩の筋肉が常に緊張しやすく、筋トレ時にも首を痛めるリスクが高まります。
セルフチェック|あなたはストレートネック?
ご自身がストレートネック傾向にあるか、簡単にセルフチェックしてみましょう。
壁を使った方法がおすすめです。まず、かかと・お尻・肩甲骨を壁に付けて直立し、力を抜いてみてください。
このとき後頭部まで自然に壁に付けば理想的な姿勢ですが、後頭部が壁から離れてしまう場合や、無理に顎を引かないと付かない場合はストレートネックの可能性が高いです。
このセルフチェックで首のカーブの状態を確認し、日常から姿勢を意識するきっかけにしましょう。
姿勢が悪いと筋トレフォームも崩れる
ストレートネックに限らず、猫背や反り腰など日頃の姿勢の癖はそのまま筋トレのフォームにも表れます。
例えば猫背・頭突出(いわゆるスマホ首)の人は、肩関節や胸の筋肉が硬くなりがちで、ベンチプレス時に肩甲骨を寄せにくかったり、ショルダープレス時に頭が前に出てバーベルの軌道が不安定になったりします。
その結果、首に余計な負荷がかかって痛みを誘発することがあります。つまり「普段の姿勢」=「身体のクセ」であり、そのクセが筋トレ中の動作を歪めてしまうのです。
逆に言えば、日常から姿勢を正すことで筋トレのフォーム改善にもつながります。スマホを見るときは目の高さまで上げてうつむき姿勢を避ける、長時間同じ姿勢を続けない、デスクワークでは椅子に深く腰掛けて背筋を伸ばす等、姿勢維持の工夫を取り入れてみましょう。
姿勢が整えば筋トレ時の動きもスムーズになり、首への負担軽減とパフォーマンス向上の一石二鳥が期待できます。
首が痛い時の応急処置|冷やす?温める?
「首を痛めてしまった!すぐ冷やすべきか、それとも温めた方がいいのか…?」と迷うことがあります。
適切な応急処置は、痛みの原因や発生からの経過時間によって異なります 。
原則として急性期のケガで炎症が起きている場合は冷却(アイシング)、慢性期の痛みや筋肉のこわばりには温熱療法が有効です。首の痛みに対して正しく対処するため、冷やす場合・温める場合のポイントをそれぞれ確認しましょう。
冷やすタイミングと時間の目安
筋トレ中や直後に首をひねった、筋を違えたといった急性の痛みには、まず冷やす処置が勧められます。
急性期とは痛みが出始めた直後から数日以内のことで、受傷後おおむね2~3日間が目安です。この時期は患部で炎症反応が起こり、腫れや熱感を伴うため、温めるとかえって症状が悪化する恐れがあります。冷やすことで炎症を抑え、痛みや腫れの拡大を防ぐことができます。
具体的なアイシング方法としては、氷嚢(ひょうのう)や氷を入れたビニール袋をタオルで包んで患部に当てると良いでしょう。
どれくらい冷やす?– 公益財団法人スポーツ安全協会の救急処置ハンドブックによれば、アイシングは「1回20分程度」を目安に行います。
ケガ直後の初日は1時間おきに、2~3日目は1日6回程度を目安に繰り返し冷やすと効果的とされています。長時間当てっぱなしにするのではなく、適度に間隔をあけながら冷却しましょう。
氷で冷やすと患部の感覚が麻痺して痛みが和らぎ、筋肉の緊張も鎮める効果があります 。炎症が収まるまでの数日間は安静を保ちつつ、このアイシング処置を続けることで回復を早めることができます。
温めるべき症状とその方法
一方、慢性的な痛みやコリには温めるケアが適しています。急性期を過ぎて炎症が治まった痛みは、筋肉の血行不良やこわばりが原因であることが多く、温めて血流を促進することで症状が改善しやすくなります。
目安として受傷から2~3日経ち、患部に熱感や腫れがなければ温めに切り替えるタイミングです。具体的には、蒸しタオルやカイロを首の痛む部分に当てたり、入浴時にしっかり温めたりすると良いでしょう。
温熱によって筋肉がほぐれ、血液循環が改善すると、痛めた組織に酸素や栄養が行き渡り回復を促進します 。
注意点*– 温める場合も、患部を強くマッサージしすぎないよう注意してください。特に痛みが残るうちは優しく温めるだけに留め、ストレッチなどは無理のない範囲で行いましょう。
なお、温めている途中でズキズキ痛みが増すようなら炎症が残っている可能性があります。その場合は再度冷却に戻すなど、痛みの状態を見ながら対応してください 。急性期には冷やし、慢性期には温める——この基本を覚えておくと、首に限らず捻挫や打撲など様々なケガの応急処置に役立ちます。
トレーニング再開の判断基準と注意点は?
首を痛めた後、いつからトレーニングを再開して良いか迷うところです。再開の判断を誤ると痛みを長引かせたり再発させたりしかねないため、慎重に見極めましょう。ここでは、痛みが軽度の場合にできるトレーニング例と、痛みを再発させないためのフォーム習得・ケアのポイントを紹介します。
軽度の痛みならできるトレーニングとは?
痛みがごく軽く、日常動作でほとんど支障がない程度であれば、首に負荷をかけない範囲でトレーニングを再開してもよいでしょう。ただし無理は禁物です。
例えば、上半身の激しいウェイトトレーニングは控え、代わりに下半身の種目(スクワットやレッグプレス等)や有酸素運動から様子を見る方法があります。
下半身の運動であれば首への直接的な負担は少なく、体を動かす感覚を維持しながら回復を待つことができます。また、首の痛みが軽減してきたら、リハビリも兼ねて首や肩周りのストレッチを取り入れるのも有効です 。ゆっくりと首を前後左右に動かすストレッチや、痛みがなければ軽い負荷でのシュラッグ(肩をすくめる運動)などで僧帽筋をほぐすのもよいでしょう。
ただしストレッチや運動中に痛みが強まる場合は直ちに中止してください。痛みが残っているうちは「痛みが出ない範囲で軽めの運動」にとどめ、決して無理に通常通りの負荷に戻さないことが大切です。
痛みを再発させないフォーム習得法
首の痛みを再発させないためには、根本原因であるフォームの改善と日々のケアが重要です。まずフォーム習得については、鏡やスマートフォンの動画機能を使って自分のトレーニングフォームをチェックしましょう。
客観的に見ることで、首が前に出ていないか、肩がすくんでいないかなど問題点が把握できます。可能であればトレーナーや経験者にフォームを見てもらい、フィードバックを受けると安心です。
一朝一夕で癖を直すのは難しいですが、軽い重量から練習し正しい動きを身体に覚え込ませることで徐々にフォームは改善します。フォームが安定すれば不要な首の緊張も減り、再び痛めるリスクは下がるでしょう。
また、トレーニング前後のケアも欠かせません。ウォーミングアップでは首・肩周りを含め全身をほぐしておき、いきなり高負荷をかけないようにします。トレーニング後はクールダウンとしてストレッチやアイシングを行いましょう。
スポーツ安全協会も「痛い部分を冷やすことで痛みと筋肉のこわばりを減らせる」として、慢性的な痛みに対するアイシングを練習後のメニューに取り入れることを推奨しています。
実際、練習後に患部を10~20分冷やす習慣をつけるだけでも、筋肉痛や故障の予防に有効です。さらに普段から適度な休養をとり、首や肩の疲労をため込まないことも大切です。定期的なストレッチや整骨院でのメンテナンス等、自分なりのケア方法を継続していきましょう。
医療機関に行くべき症状とは?整形外科と整骨院の違い
「首の痛みで病院に行くべきか、整骨院で様子を見るべきか」悩む方もいるでしょう。ここでは、受診の目安となる症状と、整形外科と整骨院(接骨院)の役割の違いについて解説します。
受診の目安|整形外科と整骨院の違いとは?
まず、次のような症状がある場合は整形外科(病院の整形外科医)を受診しましょう。で示されるように、首を動かすと強い痛みが走る、腕や手にしびれ・力が入らない等の神経症状を伴う場合は頚椎の椎間板ヘルニアや神経圧迫の可能性があります。
こうした症状や、痛みが数日たっても全く改善しない場合は、できるだけ早めに整形外科で診察を受けることをおすすめします。また、痛みとともに首や後頭部にかつてない激痛が突然起こった場合(いわゆる激烈な痛み)は、稀に動脈の解離など緊急疾患の可能性もあるため迷わず救急外来を受診してください 。
整形外科ではレントゲンやMRIなどの画像検査により骨・関節の異常を確認でき、必要に応じて投薬や注射、リハビリ指導など医学的アプローチで治療が受けられます。
健康保険も基本的に適用され、慢性的な肩こりや痛みに対する相談も可能です。痛みの根本原因を正確に知り、専門的な治療や診断を受けたい場合は整形外科が適切と言えます。
一方で、「動かせるけれど首をひねって痛めてしまった」「軽い寝違え程度だが早く治したい」といった筋肉や関節の軽いケガであれば、整骨院(接骨院)を利用する選択肢もあります。整骨院では国家資格である柔道整復師が徒手による施術(いわゆる骨盤矯正やマッサージ、テーピングなど)を行い、捻挫・挫傷(筋違い)などの改善を図ります。
ただし、整骨院は医師ではないためレントゲン検査や痛み止めの処方はできず、対応できる範囲は「急性または亜急性の外傷性の負傷」に限られています。実際、健康保険が適用されるのも急性のケガのみであり、日常生活からくる慢性的な首や肩のこり・痛みは保険適用外で自費扱いになります。
長年の肩こり解消目的で整骨院に通いたい場合などは全額自己負担となる点に注意が必要です。逆に言えば、筋トレ中に首を捻った・寝違えのような急性の負傷であれば整骨院で保険適用の施術が受けられる場合があります。症状に応じて整形外科と整骨院を使い分けましょう。
併用はできる? – 整形外科と整骨院を両方受診する場合、同じ負傷についての重複受診は避けるべきです 。例えば整形外科で「安静に」と言われたケガを、許可なく整骨院で並行して施術してもらうことは医療費の無駄遣いになるだけでなく、保険請求上も問題となります。
まずは整形外科で検査・診断を受け、骨には異常がないが筋肉の張りが強いといった場合に、医師の了承のもと整骨院でリハビリや施術を受ける、といった形が望ましいでしょう。なお、整体院やカイロプラクティックは法律上の国家資格を持たない施術所であり、これらは保険適用もできません。同じ「首のケア」を掲げていても資格や制度が異なるため、利用の際は注意してください。
保険適用されるのはどんなケース?
整形外科と整骨院の保険適用ルールについて整理しておきます。整形外科では医療機関ですので、首の捻挫や椎間板ヘルニアなど診断された傷病に対して基本的に健康保険が適用されます。慢性的な肩こりであっても、症状緩和のための投薬やリハビリには保険診療が使われることがあります。
一方、整骨院で保険が使えるのは前述のとおり「急性のケガ」のみです。例えば筋トレ中に首を捻挫した、転倒して打撲した、といったケースでは整骨院での施術に保険が適用されますが、原因のはっきりしない慢性痛や疲労性のコリには適用されません。整骨院の窓口で「各種保険取扱」と書かれていても、それはあくまで急性外傷の場合に限られる点を覚えておきましょう。
また、保険適用で整骨院にかかる場合は施術内容を健康保険組合等がチェックしており、後日受診者に施術内容の確認が届くこともあります 。これは不正請求防止のための仕組みですので、正当に利用していれば問題ありません。いずれにせよ、まずは自分の首の痛みが「急性のケガ」か「慢性的な痛み」かを見極め、急性なら整骨院も活用、判断に迷う場合や長引く痛みなら整形外科で専門医の診断を仰ぐ、といった使い分けが賢明です。
まとめ|首の痛みと向き合いながら筋トレを続けるには?
首の痛みは筋トレ愛好者にとって悩ましい問題ですが、正しい知識と対策があれば乗り越えることができます。まず何より大切なのは痛みの原因を把握し、無理をしないことです。
「首が痛いけど根性で続けよう…」ではなく、原因がフォームなのか負荷なのか、それともストレートネックなど身体の問題なのかを見極めましょう。
痛みを感じたら一旦トレーニングを中断し、必要に応じてアイシングなどの応急処置を行います。異常な痛みや体調不良を感じたときは我慢せずトレーナーや周囲に伝え、必要なら医療機関で適切な診断・治療を受けることも大切です。
次に、正しいフォームと姿勢の習慣づけを日頃から意識しましょう。ストレートネックや猫背を改善する取り組みは、筋トレ時のパフォーマンス向上のみならず日常生活の健康にもつながります。
軽い痛みが出た場合でも、紹介したセルフチェックやストレッチを活用して早めにケアすることで悪化を防ぐことが可能です。逆に放置して慢性化すると治りにくくなりますので、「おかしいな?」と思った時点でケアを始めることが肝心です。
そして、継続したケアと予防策も忘れずに。トレーニング前の準備運動から後のクールダウンまで、一連の流れの中で首や肩への気配りを習慣化しましょう。幸い、公的機関からも推奨されているようにアイシングやストレッチなど簡単にできる対策が数多くあります。
これらを取り入れることで、首の痛みと上手に付き合いながら筋トレを続けることが十分可能です。 痛みの克服には時間がかかるかもしれませんが、正しい対策を積み重ねれば必ず改善に向かいます。首ともうまく対話しつつ、無理なくトレーニングを継続していきましょう。そうすれば、首の痛みに悩まされない快適な筋トレライフがきっと手に入るはずです。
参考文献
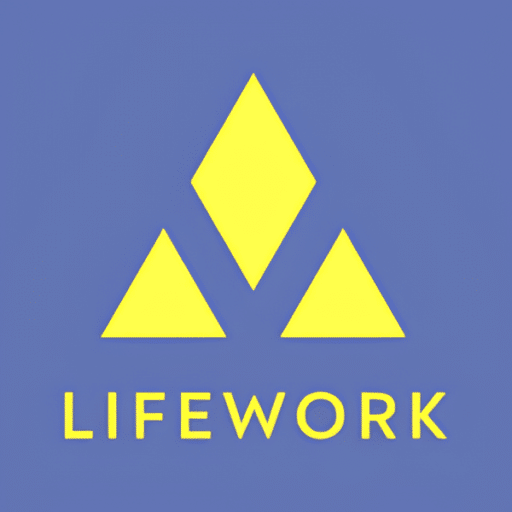





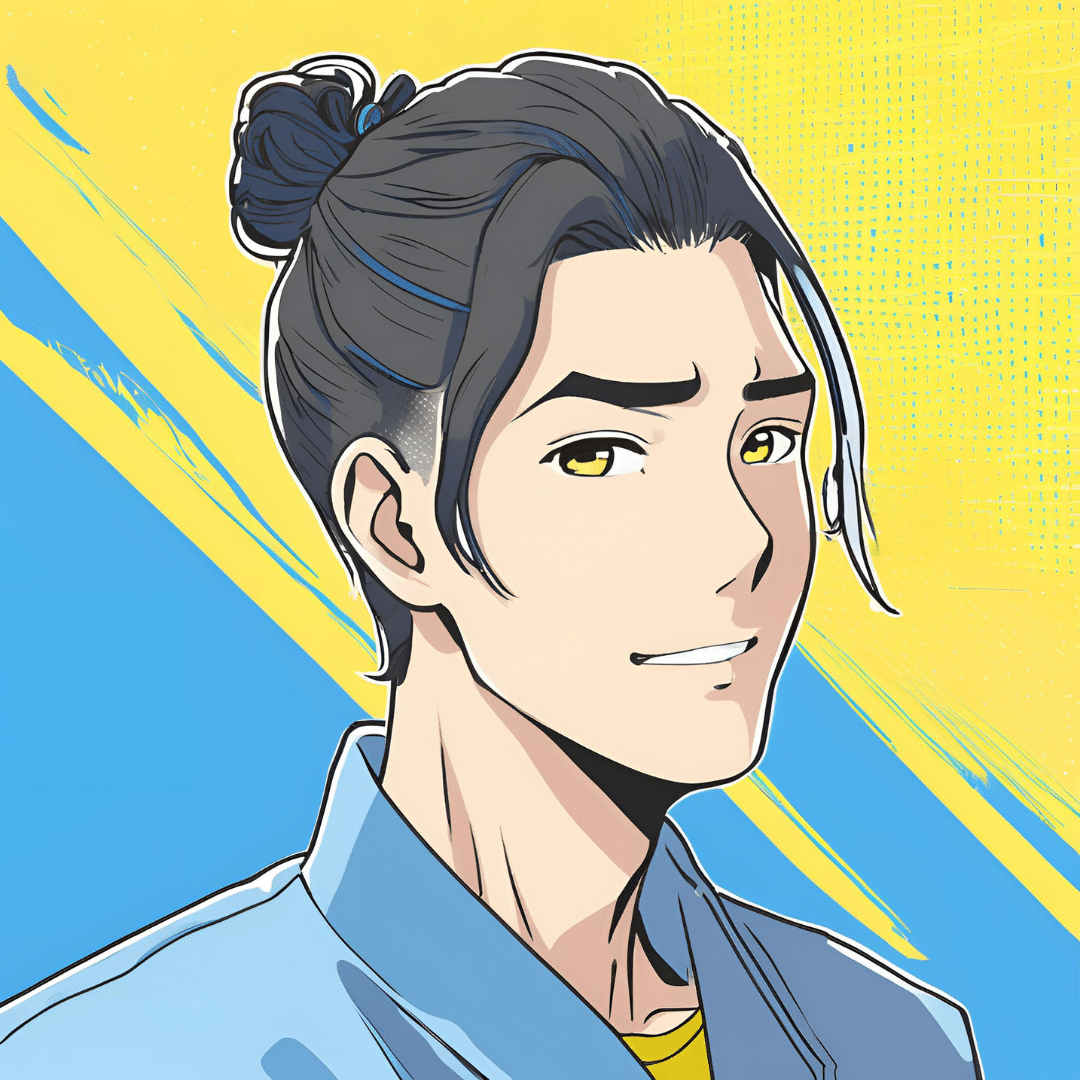



コメント