筋トレは何セットやるべき?目的別に最適な回数を解説
筋トレを始めると必ず直面する疑問が「何セットやればいいのか?」というものです。ネット上には「1セットで十分」という情報もあれば、「最低5セットは必要」という真逆の意見まで溢れていて、何を信じればいいのか迷ってしまいますよね。
この記事では、科学的根拠に基づいて、あなたの目的や経験レベルに合わせた最適なセット数を徹底解説します。筋肥大を目指す方、ダイエット中の方、健康維持が目的の方など、それぞれのニーズに応える内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
筋トレは何セットやればいい?目的別のセット数目安
結論から言うと、「筋トレの最適なセット数」は以下の要素によって大きく変わります。
- トレーニングの目的(筋肥大・筋力アップ・ダイエット・健康維持など)
- トレーニング経験(初心者・中級者・上級者)
- 対象とする筋肉部位(大筋群・小筋群)
- 年齢や回復力
- 利用できる時間
それでは、目的別に最適なセット数について詳しく見ていきましょう。
【筋肥大】1種目何セットがベスト?科学的根拠と回数の目安
筋肥大(筋肉を大きくすること)を目指すなら、科学的研究では週あたりの総セット数が重要視されています。アメリカスポーツ医学会(ACSM)の最新ガイドラインによれば、筋肥大に最適な週間セット数は以下の通りです。
- 初心者:週あたり各部位10〜12セット
- 中級者:週あたり各部位13〜15セット
- 上級者:週あたり各部位16〜20セット以上
これを1回のトレーニングセッションに換算すると、部位あたり3〜5セットが理想的です。例えば、週2回胸を鍛えるなら、1回のトレーニングで3〜5セット行い、週トータルで6〜10セットになるよう調整するといいでしょう。
ただし、セット数だけでなく「総負荷量」という概念も重要です。これは「重量×回数×セット数」で計算されるもので、筋肥大に必要な刺激量を表します。
最新の研究では、1セットでも限界まで追い込めば効果はあるものの、複数セット(3〜5セット)行うことで筋肥大効果が最大化することがわかっています。特に自然な状態でトレーニングする場合(ステロイドなどを使用しない場合)は、適切なセット数の確保が重要です。
【ダイエット】セット数と回数の適切な組み合わせ
ダイエット目的の場合、カロリー消費と代謝アップの両面から考える必要があります。効率的な脂肪燃焼を促すには、以下のセット構成が効果的です。
- セット数:3〜4セット
- 回数:10〜15回
- インターバル:30〜60秒(短めに設定)
ダイエット中は全身運動やコンパウンド種目(複数の筋肉を同時に使う運動)を中心に組み立て、サーキット形式でトレーニングすると時間効率が上がります。例えば、以下のようなサーキットを3〜4セット行うのがおすすめです。
- スクワット:12回
- プッシュアップ:10回
- ローイング:12回
- プランク:30秒
各種目間の休憩は最小限(15〜30秒程度)にして、1セット終了後に1分休憩するというパターンです。このようなトレーニングなら、40分程度で十分な運動量を確保できます。
また、HIIT(高強度インターバルトレーニング)と組み合わせると、脂肪燃焼効果が長時間持続する「EPOC効果」も期待できます。
【健康維持】筋トレ初心者・高齢者は1セットでもOK?
健康維持や基礎体力向上を目的とする場合、特に初心者や高齢者は1セットでも十分効果があります。アメリカ国立衛生研究所(NIH)の研究では、週2〜3回、1種目1セット(8〜12回)のトレーニングでも、筋力や健康指標の改善が見られることが確認されています。
高齢者(65歳以上)の場合は、以下のようなガイドラインが推奨されています:
- セット数:1〜2セット
- 回数:10〜15回(やや軽めの重量)
- 頻度:週2〜3回
- 種目数:8〜10種目(全身をバランスよく)
高齢になるほど回復に時間がかかるため、無理にセット数を増やすより、適切なフォームで安全に行うことが優先されます。また、関節への負担を考慮し、マシンを活用したトレーニングも有効です。
ただし、健康維持を超えて筋力アップや見た目の変化を求めるなら、徐々にセット数を2〜3セットに増やしていくことをおすすめします。
初心者が筋トレを始めるときのセット数と種目数は?
筋トレ初心者がよく陥る失敗は、最初から多くのセット数や種目に挑戦しすぎることです。これは怪我のリスクを高めるだけでなく、続けられない原因にもなります。では、初心者はどのようにスタートすべきでしょうか?
初心者が1種目3セットから始めるべき理由とは?
初心者が1種目3セットから始めるべき理由は主に以下の3つです。
- 適応期間の確保:
筋肉だけでなく、神経系や腱・靭帯などの結合組織もトレーニングに適応する時間が必要です。3セットなら十分な刺激を与えつつも、過剰な負担を避けられます。 - フォーム習得の機会:
1セット目で動きを確認し、2セット目で修正、3セット目で定着させるという流れが作れます。これにより怪我のリスクを下げながら効果的なトレーニングができます。 - 疲労管理と継続性:
初心者は特に筋肉痛が強く出やすいため、過度なセット数は日常生活に支障をきたす恐れがあります。3セットなら適度な疲労感と達成感のバランスが取れます。
「初心者は最初から5セット以上やるべき」という情報もありますが、これは科学的根拠に乏しく、むしろ逆効果になる可能性が高いです。持続可能なトレーニング習慣を作るためにも、まずは1種目3セットを8週間ほど続けてから、徐々にセット数を増やしていくのが賢明です。
部位ごとのセット数一覧表【初心者向け】
初心者の方向けに、部位別の推奨セット数をまとめました。週2回のフルボディトレーニングを想定しています。
筋肉部位1回あたりのセット数週間総セット数おすすめ種目胸筋3セット6セットベンチプレス、プッシュアップ背筋3セット6セットラットプルダウン、ローイング脚部3セット6セットスクワット、レッグプレス肩2セット4セットショルダープレス、サイドレイズ腕(上腕二頭筋)2セット4セットダンベルカール腕(上腕三頭筋)2セット4セットプッシュダウン腹筋2セット4セットクランチ、プランク
この表を目安に、1回のトレーニングで40〜50分程度を目標にするといいでしょう。あまり長時間のトレーニングは、特に初心者の場合、疲労蓄積やモチベーション低下につながります。
上記のような構成で4〜6週間トレーニングを続けた後、徐々にセット数を増やしていくことをおすすめします。例えば、胸・背中・脚を4セットに、肩・腕・腹筋を3セットに増やすといった具合です。
上級者・中級者はセット数をどう増やすべき?
筋トレ経験が1年以上ある中級者や、3年以上のベテラントレーニーは、初心者とは異なるアプローチが必要になります。特に「プラトー」と呼ばれる停滞期を打破するためには、トレーニング変数の調整が不可欠です。
中級者が筋肥大するための週単位のセット数計算法
中級者(トレーニング歴1〜3年程度)が効果的に筋肥大を進めるには、週単位でのセット数管理が重要です。最新の研究では、以下の計算式が提案されています。
週間最適セット数 = 体重(kg) × 0.15 × 筋群係数筋群係数は部位によって異なり、大きな筋群ほど高い値になります:
- 大筋群(胸・背中・脚):1.0
- 中筋群(肩・腕):0.8
- 小筋群(腹筋・前腕など):0.6
例えば、体重70kgの場合:
- 胸の週間セット数 = 70 × 0.15 × 1.0 = 約10.5セット
- 上腕二頭筋の週間セット数 = 70 × 0.15 × 0.8 = 約8.4セット
これを週2回のトレーニングで分割するなら、1回のトレーニングで胸は5〜6セット、上腕二頭筋は4セットが目安となります。
また、中級者になると「ボリュームの漸進的過負荷」という概念も重要になります。単に重量を増やすだけでなく、セット数も計画的に増やしていく必要があるのです。
例えば8週間のプログラムであれば:
- 1〜2週目:基本セット数(上記計算式)
- 3〜4週目:各部位+1セット
- 5〜6週目:各部位+2セット
- 7〜8週目:各部位+1セット(ディロード期間)
このようにして、身体に適度なストレスをかけながら回復も確保する周期的なアプローチが効果的です。
上級者のセット数が多すぎると逆効果になる理由
上級者(トレーニング歴3年以上)は高い負荷に耐えられる身体を持っていますが、だからといってセット数を際限なく増やせばいいというわけではありません。実際、セット数が多すぎると以下のような問題が生じます。
- オーバートレーニング症候群:
過剰なトレーニングボリュームは中枢神経系に大きな負担をかけ、慢性的な疲労、パフォーマンス低下、免疫機能の低下などを引き起こす可能性があります。 - ホルモンバランスの乱れ:
過度なセット数は、筋肥大に重要なテストステロンとコルチゾールのバランスを崩し、アナボリック(同化)状態からカタボリック(異化)状態へと身体を傾けてしまいます。 - 回復能力の超過:
上級者でも回復能力には限界があります。特に自然な状態(薬物不使用)でトレーニングしている場合、週あたり各部位20〜25セット以上のトレーニングは回復が追いつかないケースが多いです。
研究によれば、上級者の最適セット数は週あたり各部位16〜20セットとされています。これ以上増やしても追加の効果は限定的で、むしろリスクが高まるという結果が出ています。
上級者向けの賢い戦略は、単にセット数を増やすのではなく、「高強度テクニック」を活用することです。例えば:
- レスト・ポーズ法
- ドロップセット
- スーパーセット
- 部分反復法
これらのテクニックを用いることで、少ないセット数でも高い刺激を筋肉に与えられます。また、定期的な「ディロード週間」(トレーニング強度を意図的に下げる期間)を設けることも、長期的な進歩には不可欠です。
1セット vs 3セット vs 5セット、効果が高いのは?
筋トレのセット数に関する永遠の議論といえば、「1セットvs複数セット」の対立です。特に「山本式」と呼ばれる1セットトレーニングの普及により、この議論は活発になりました。では、実際のところどうなのでしょうか?
山本式トレーニングは本当に1セットでいいのか
山本式トレーニングは、山本義徳氏が提唱する「超高強度1セット方式」のトレーニング法です。その主な特徴は:
- 各種目1セットのみ
- 完全失敗(フェイルアウト)まで追い込む
- 高重量・低回数(6〜8回程度)
- 種目間の休憩は最小限
この方法は、通常の3〜5セット方式と比べて時間効率が良く、高強度の刺激を与えられるというメリットがあります。しかし、実際の効果については以下の点を考慮する必要があります。
山本式の有効性:
- 中上級者には一定の効果がある
- 時間がない人には実用的
- 神経系の発達に効果的
山本式の限界:
- 初心者にはフォーム習得の機会が少ない
- 総負荷量(重量×回数×セット)が少なくなりがち
- 筋肥大に必要な「代謝ストレス」が不足する可能性
実際、山本氏自身も「全ての人に1セットを推奨しているわけではない」と述べています。彼の主張は「1セットでも効果はある」というものであり、「1セットが最適」ということではありません。
個人差や目的によって最適な方法は変わるため、1セット方式を試してみて効果を感じられるなら続ける価値はあるでしょう。特に時間効率を重視する場合や、回復力が落ちている時期には有効かもしれません。
科学的に推奨される最適セット数は3セット?5セット?
複数の科学研究を総合すると、筋肥大に関しては以下のような傾向が見られます:
- 1セット vs 複数セット:
メタ分析(複数の研究結果をまとめた分析)によれば、複数セットは1セットと比較して約40%高い筋肥大効果をもたらすことが示されています。 - 3セット vs 5セット:
初心者から中級者レベルでは、3セットと5セットの間に統計的に有意な差は見られないケースが多いです。しかし、上級者レベルになると5セット(あるいはそれ以上)の方が効果的という研究結果もあります。 - セット数と回復力:
若年層(20代)は5セットでも回復が早いですが、40代以降は3セット程度が回復力とのバランスが取れるという研究も報告されています。
科学的エビデンスを総合すると、以下のような結論になります:
- 初心者:1〜3セット(まずは形を覚える)
- 中級者:3〜4セット(基本)
- 上級者:3〜5セット(状況に応じて変動)
ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個人の回復力や目標、時間的制約などによって調整する必要があります。また、上級者ほど「週間総セット数」の概念を重視し、1回のトレーニングセット数よりも週トータルでの刺激量をコントロールするという観点が大切です。
最新の研究トレンドとしては、「個人に合わせた最小有効量(MED: Minimum Effective Dose)」を見つけるアプローチが注目されています。つまり、「あなたにとって効果が出る最小限のセット数」を見つけることが重要なのです。
コンパウンド種目・アイソレーション種目でセット数は違う?
筋トレの種目は大きく分けて「コンパウンド種目」と「アイソレーション種目」に分類されます。これらの種目タイプによって、最適なセット数は異なるのでしょうか?
コンパウンド種目(ベンチプレス等)に適したセット数
コンパウンド種目とは、複数の関節を動かし、多くの筋肉群を同時に使う複合運動のことです。代表的な種目には以下があります:
- ベンチプレス(胸・肩・三頭筋)
- スクワット(脚全体・体幹)
- デッドリフト(背中・脚・体幹)
- オーバーヘッドプレス(肩・三頭筋)
- チンニング(懸垂)(背中・二頭筋)
これらのコンパウンド種目の特徴は、高い負荷をかけられること、ホルモン分泌を促進すること、時間効率が良いことなどが挙げられます。一方で、神経系や全身への疲労も大きいという特徴もあります。
コンパウンド種目に適したセット数は、経験レベルによって異なります:
- 初心者:2〜3セット(フォーム習得を優先)
- 中級者:3〜4セット(筋力・筋肥大の両立)
- 上級者:4〜5セット(状況に応じて調整)
特にスクワットやデッドリフトのような大きな筋群を使う種目は、セット数が増えるほど疲労も蓄積されるため、他のトレーニングにも影響します。そのため、トレーニングの最初にコンパウンド種目を配置し、適切なセット数で行うことが重要です。
例えば、筋肥大を目的とする中級者のベンチプレスセッションは:
- ウォームアップ:軽い重量で2セット
- 作業セット:3〜4セット×8〜10回
- セット間休息:2〜3分
このようなアプローチが効果的です。また、コンパウンド種目は週に2回行う場合、1回目は重量重視(4〜6回×4セット)、2回目は代謝ストレス重視(10〜12回×3セット)というように変化をつけるのも効果的です。
アイソレーション種目(カール等)の効果的セット数
アイソレーション種目とは、単一の関節を動かし、特定の筋肉を集中的に鍛える種目のことです。代表的なものには:
- ダンベルカール(上腕二頭筋)
- トライセプスエクステンション(上腕三頭筋)
- レッグエクステンション(大腿四頭筋)
- レッグカール(ハムストリングス)
- ラテラルレイズ(三角筋)
これらの種目は、特定の筋肉を集中的に追い込める反面、コンパウンド種目に比べて扱える重量は少なく、全身への刺激も限定的です。
アイソレーション種目に適したセット数は:
- 初心者:2セット(補助的に)
- 中級者:3セット(弱点強化に)
- 上級者:3〜4セット(細部の彫り込みに)
アイソレーション種目はコンパウンド種目の後に行うことが一般的です。これは、コンパウンド種目でパワーを使い切る前に小さな筋肉を疲労させないためです。
特に二頭筋や三頭筋などの小さな筋群は回復も早いため、セット数よりも「感覚的な追い込み」を重視するアプローチも効果的です。例えば:
- 通常セット:2〜3セット
- フィニッシングセット:1セット(ドロップセットやパンプ重視)
上級者向けテクニックとして、アイソレーション種目では「ミッドレンジパーシャル法」(関節の可動域の中間部分だけを集中的に動かす方法)などを活用し、少ないセット数でも高い刺激を得るという方法もあります。
基本的に、アイソレーション種目はコンパウンド種目と比べてセット数を1〜2セット少なくしても十分効果が得られるケースが多いです。
筋トレのセット間休憩(インターバル)は何分取るべき?
セット数と同じくらい重要なのが、セット間の休憩時間(インターバル)です。適切なインターバルを設定することで、トレーニング効果を最大化できます。
インターバルが短すぎると筋肥大には逆効果?
一般的に、「インターバルは短い方が筋肥大に効果的」という考え方がありますが、これは必ずしも正確ではありません。実際、インターバルが短すぎると以下のようなデメリットが生じる可能性があります:
- 総負荷量の減少:
十分な休息がないと、後続のセットで扱える重量やこなせる回数が大幅に減少します。結果として総負荷量(重量×回数×セット)が減り、筋肥大刺激が不足する恐れがあります。 - フォームの崩れ:
疲労した状態で次のセットを行うと、正しいフォームを維持できなくなり、効果的に標的筋群を刺激できないだけでなく、怪我のリスクも高まります。 - 無酸素系エネルギーの枯渇:
筋肥大に重要なATP-PCrシステム(無酸素性エネルギー源)は、完全回復に約3分かかります。休憩時間が短すぎると、このシステムが十分に回復せず、最大筋力発揮が難しくなります。
ある研究では、ベンチプレスにおいて1分休憩のグループと3分休憩のグループを比較したところ、3分休憩のグループの方が12週間後の筋力増加が有意に大きかったという結果も報告されています。
つまり、「短いインターバル=高い代謝ストレス=良い筋肥大」という単純な図式は必ずしも正しくないのです。筋肥大にはある程度の休息時間確保が必要なケースが多いようです。
最新研究から見た理想的なインターバル時間とは
2020年以降の最新研究を総合すると、目的別の理想的なインターバル時間は以下のように整理できます:
筋力向上が目的の場合:
- 高重量(1〜5RM):3〜5分
- 中重量(6〜8RM):2〜3分
筋肥大が目的の場合:
- 大筋群(胸・背中・脚):2〜3分
- 小筋群(腕・肩・腹筋):1〜2分
持久力・引き締めが目的の場合:
- 高回数トレーニング:30秒〜1分
- サーキットトレーニング:30秒以下
また、セット間インターバルの設定は「主観的疲労感」も考慮するとよいでしょう。例えば「息が整い、心拍数が落ち着いたと感じたら次のセットへ」というように、自分の回復状態に合わせて調整する方法も有効です。
その他、インターバルに関する実践的なポイントとして:
- アクティブレスト:
完全に動きを止めるのではなく、軽いストレッチや関節の動的ストレッチを行うことで、血流を維持しながら回復を促進できます。 - インターバルタイマーの活用:
スマートフォンアプリなどでタイマーを設定することで、休憩時間の管理が容易になります。主観だけだと、必要以上に長く休んでしまうケースも多いです。 - 段階的インターバル法:
セットが進むにつれて休息時間を延ばす方法。例えば1セット目と2セット目の間は2分、2セット目と3セット目の間は2.5分、3セット目と4セット目の間は3分というように設定します。
こうした最新の知見を活かし、目的に合わせたインターバル設定を行うことで、トレーニング効果を最大化できるでしょう。年齢や性別で筋トレのセット数は変えるべき?
トレーニングプログラムを設計する際、年齢や性別という要素も考慮すべきでしょうか?実は、これらの要因はセット数設定に少なからぬ影響を与えます。
年代別(20代/40代/60代)の最適セット数比較表
年齢によって回復能力やホルモン環境が異なるため、適切なセット数も変わってきます。以下に年代別の目安をまとめました。
| 年代 | 筋肥大目的 | 筋力向上目的 | 健康維持目的 | 週間トレーニング頻度 | 回復期間の目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20代 | 3〜5セット | 4〜6セット | 2〜3セット | 週4〜5回 | 24〜48時間 |
| 40代 | 3〜4セット | 3〜5セット | 2〜3セット | 週3〜4回 | 48〜72時間 |
| 60代 | 2〜3セット | 2〜4セット | 1〜2セット | 週2〜3回 | 72〜96時間 |
20代はテストステロンや成長ホルモンのピーク期であり、高い回復力を持っています。そのため、比較的高いセット数でもしっかり回復でき、効果を発揮できるのが特徴です。例えば、胸のトレーニングで20代であれば週に15セット程度(1回のトレーニングで5セット×週3回)も可能です。
一方、40代になるとホルモン環境の変化により回復に時間がかかるようになります。過度なセット数は逆に停滞を招く恐れがあるため、質を重視したアプローチが効果的です。例えば、超高強度の3〜4セットに絞り、十分な休息日を確保するといった方法が推奨されます。
60代以上になると、筋繊維の萎縮や関節の問題に注意する必要があります。少ないセット数でも確実に効かせることを重視し、フォームの完成度や適切なテンポに焦点を当てましょう。特に怪我予防の観点から、ウォームアップに時間をかけ、本セットは2〜3セットに抑えるのが安全です。
あるスポーツ医学の研究では、「60歳以上のトレーニーは、若年層の70%程度のボリュームで同等の刺激効果が得られる」という興味深い結果も報告されています。つまり、年齢に応じたセット数の調整は科学的にも理にかなっているのです。
男女で筋トレセット数は違うのか?
性別によるトレーニング設計の違いについては、様々な見解がありますが、最新の研究からは以下のような傾向が見られます。
基本的に、筋力トレーニングのメカニズムに男女差はそれほど大きくありません。しかし、ホルモン環境や筋繊維タイプの分布に違いがあるため、最適なセット数やトレーニング設計にはいくつかの調整ポイントがあります。
女性のトレーニング特性:
- エストロゲンの影響で回復が比較的早い
- 高回数・中強度トレーニングに対する反応が良い
- 上半身と比較して下半身の筋力発達が早い
- 男性より筋肉痛が出にくい傾向
男性のトレーニング特性:
- テストステロンの影響で上半身の筋発達が早い
- 低回数・高強度トレーニングに対する反応が良い
- 絶対的な最大筋力の上限が高い
- 高重量トレーニングの回復に時間がかかる
これらの特性から、一般的に推奨されるセット数に若干の差が生じます。例えば:
女性の場合:
- 上半身:3〜4セット(男性より1セット多め)
- 下半身:2〜3セット(回復力が高いため)
- 頻度:同じ部位を週2〜3回トレーニング可能
男性の場合:
- 上半身:2〜3セット
- 下半身:3〜5セット(相対的に発達が遅いため)
- 頻度:高強度トレーニング後は48〜72時間の回復期間が理想的
ただし、これらはあくまで一般的な傾向であり、個人差の方が大きい場合も多いです。専門的なトレーニングを始めて6カ月以上経過したら、自分の体の反応を観察しながら最適なセット数を見つけていくのが最も効果的です。
近年の研究では、「トレーニングの基本原則は性別に関わらず同じだが、女性はボリュームトレーニング(セット数やトレーニング頻度が多い)に対する耐性が高い」という結論も出ています。つまり、女性は男性よりもやや多めのセット数でもオーバートレーニングになりにくいという特性があるのです。
まとめ|筋トレの目的とレベルでセット数を賢く調整しよう!
この記事では、筋トレのセット数に関する様々な疑問について科学的根拠に基づいて解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめておきましょう。
目的別の最適セット数
- 筋肥大目的:3〜5セット
- 筋力向上目的:3〜6セット
- ダイエット目的:3〜4セット
- 健康維持目的:1〜3セット
経験レベル別のガイド
- 初心者:1種目3セットからスタート
- 中級者:部位ごとに週間総セット数を管理(週10〜15セット)
- 上級者:最大20セット/週を超えないよう注意
種目タイプによる違い
- コンパウンド種目:より多めのセット数と十分な休息
- アイソレーション種目:やや少なめのセット数でも効果的
セット間インターバルの目安
- 筋力向上:2〜5分
- 筋肥大:1〜3分
- 持久力・引き締め:30秒〜1分
年齢・性別による調整
- 年齢が上がるほどセット数を減らし質を重視
- 性別による大きな差はないが、女性はやや多めのセット数に耐性がある
筋トレのセット数に「絶対的な正解」はなく、あなたの目的、体質、生活スタイルに合わせて調整していくことが大切です。最初は標準的なセット数(3セット)から始め、体の反応を見ながら微調整していくのがベストでしょう。
また、セット数だけでなく「質」も重要です。フォームの正確さ、適切なテンポ、集中力などを高めることで、少ないセット数でも高い効果を得られます。特に時間が限られている方は、「少ないセット数でも質の高いトレーニング」を心がけましょう。
最後に、トレーニングは継続することが最も重要です。自分にとって無理のないセット数で、長く続けられるプログラムを見つけることが、結果的には最も効果的なアプローチになります。焦らず、楽しみながら、自分の体と対話するように筋トレに取り組んでみてください。
セット数は筋トレの成功を左右する重要な要素ですが、それ以上に重要なのは「続けること」です。自分に最適なセット数を見つけて、理想の体を目指しましょう!
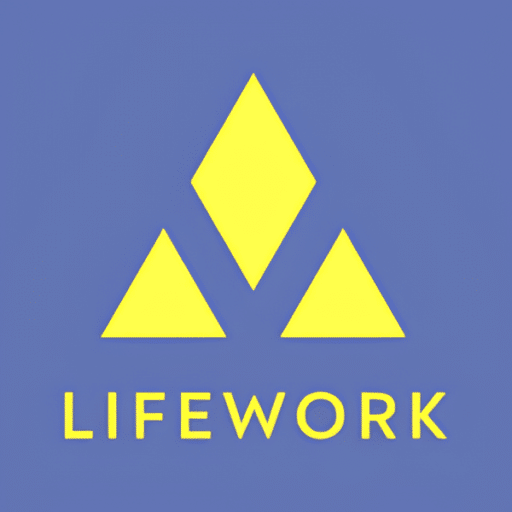





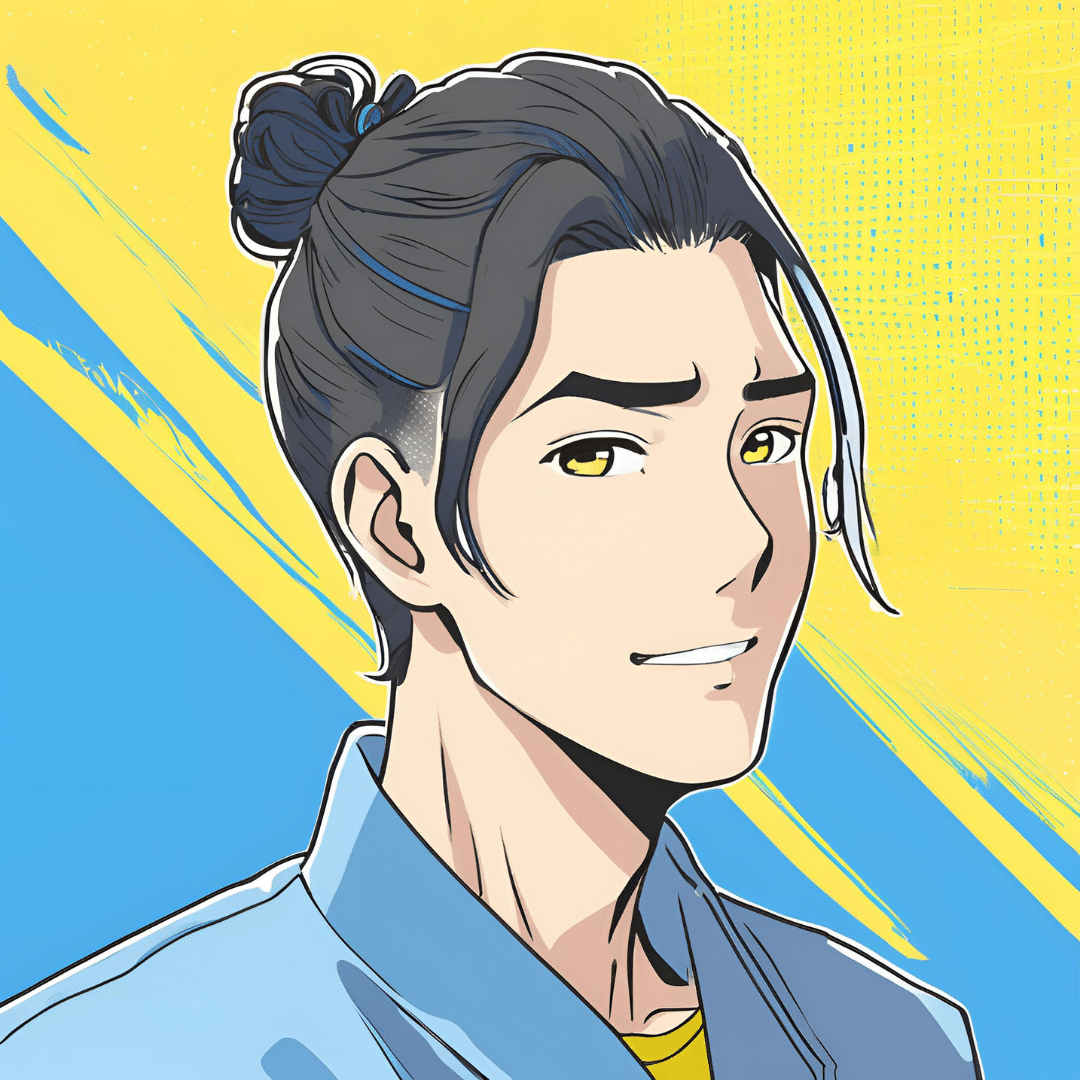








コメント